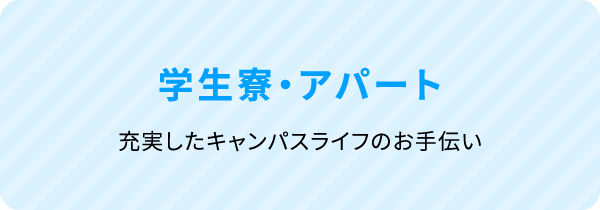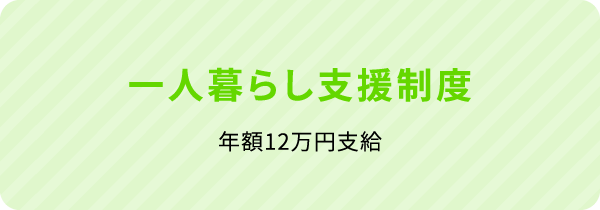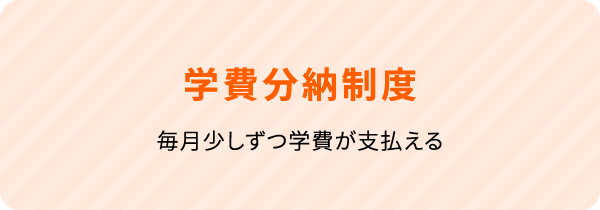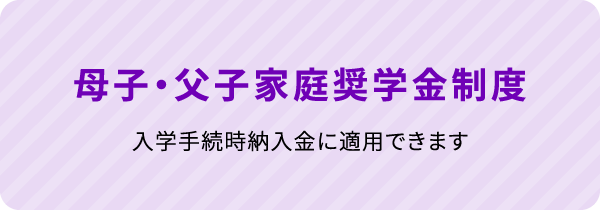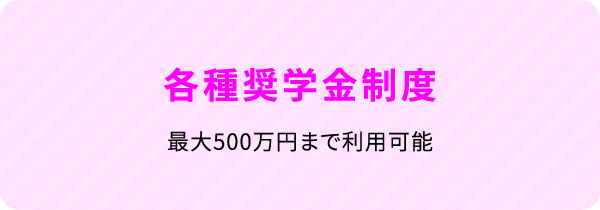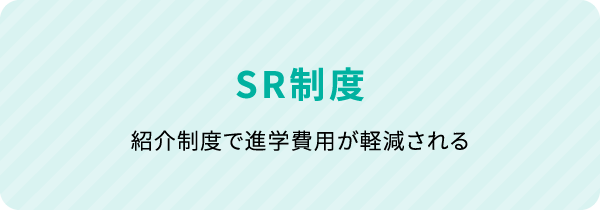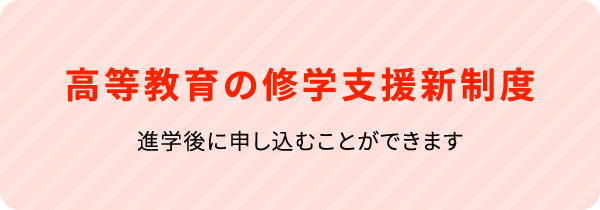映像・テレビ・映画業界
最新情報・コラム
映像業界の職種・仕事内容・将来性について|やめとけと言われる理由も解説
映像業界の仕事って「憧れるけど大変そう」「やめとけって聞いたことがある」なんて思っていませんか?でも実際は、映画やアニメ、YouTube、配信サービスなど活躍の場はどんどん広がっています。
この記事では、映像業界の主な職種や仕事内容、将来性、そして「やめとけ」と言われる理由についてもわかりやすく解説します!

映像業界とは
映像業界とは、映像をつくり出し、人々に届ける仕事全般を指します。
映画やドラマだけでなく、アニメ、CM、音楽PV、YouTubeや配信サービスの動画など、活躍の場はとても広いのが特徴です。
映像は「記録」「表現」「エンタメ」など様々な役割を持ち、社会や文化に大きな影響を与えています。
主な分野・メディアの例
- 映画(劇場作品、短編映画など)
- テレビ番組(ドラマ、バラエティ、ドキュメンタリーなど)
- アニメーション(TVアニメ、劇場アニメ、配信アニメ)
- 広告映像(CM、企業PR動画)
- 音楽映像(MV/ミュージックビデオ)
- 配信・Web動画(YouTube、TikTok、Netflixなど)
- イベント・舞台映像(ライブ中継、プロジェクションマッピングなど)
映像業界は多くの専門職が関わり合いながら一つの作品を完成させる、チームワークが欠かせない世界です。
映像業界の動向
近年の映像業界は、インターネットの普及とともに大きく変化しています。
これまで映画館やテレビが主な舞台でしたが、今ではYouTubeやTikTok、InstagramなどのSNSが欠かせない発信の場となっています。
個人が手軽に映像を制作・配信できるようになったことで、プロのクリエイターだけでなく一般の人からスターが生まれる時代になりました。
また、NetflixやAmazon Prime Videoといった配信サービスも急成長し、ドラマやアニメの制作現場に新しいチャンスを生み出しています。
こうした動きにより、映像の需要はさらに拡大し、仕事の幅も広がり続けているのが現状です。

映像業界が「やめとけ」と言われる理由
映画やアニメ、YouTubeなどを支える映像業界。華やかに見えるけれど「やめとけ」とも言われる世界。
その理由や魅力を紹介します。
長時間労働と不規則な勤務体系
映像業界では撮影スケジュールや納期にあわせて動くため、どうしても長時間労働や不規則な勤務になりがちです。
たとえばドラマや映画の撮影は早朝から深夜まで続くことがあり、編集作業では徹夜で映像を仕上げることも珍しくありません。
こうした働き方が「やめとけ」と言われる理由の一つです。
ただし、近年は改善の取り組みも進んでいます。働き方改革や労務管理の強化によって、制作会社によっては労働時間をシフト制にしたり、フレックスタイムを導入したりする例も出てきています。
また、映像編集ソフトや撮影機材の進化により、以前より効率よく作業できるようになってきました。まだ課題はありますが、業界全体で「働きやすさ」を重視する流れが少しずつ広がっています。
給料が低い
映像業界は「好きなことを仕事にできる」一方で、給料が低いと感じる人も少なくありません。特にアシスタントや新人の時期は、生活がぎりぎりになるほど収入が少ないケースもあり、ここが「やめとけ」と言われる理由のひとつです。
ただし、経験を積み、スキルが認められれば収入は大きく伸びていきます。
特にディレクターやカメラマン、編集のスペシャリストは高収入を得られることもあります。最近では動画配信サービスやSNS動画の需要が急増しており、企業案件やフリーランスとして仕事を受ける人が増え、収入の幅が広がる傾向にあります。
また、学校でしっかり基礎を学び、在学中からインターンやアルバイトで経験を積むことで、卒業後に即戦力として評価され、比較的良い条件でスタートできる可能性もあります。
下積み時代がキツくやりがいを感じづらい
映像業界では、多くの場合アシスタントや雑務からキャリアが始まります。
機材の準備や片付け、資料整理など「自分が思い描いたクリエイティブな仕事」からは遠い作業が多く、やりがいを感じにくいのが現実です。
このため「下積みが長くてつらい」「夢がかなわない」と言われることがあります。
しかし、この時期に学んだ現場のマナーや基本的な作業が、のちに大きな武器になります。実際にプロの現場で経験を積むことで、段階的にステップアップできるのも映像業界の特徴です。
また、最近では若手に早めに撮影や編集を任せる制作会社も増え、スキルを発揮するチャンスが広がってきています。
さらに、専門学校などで在学中から企画や作品制作を経験しておけば、現場で信頼を得やすく、下積みの期間を短縮できる可能性もあります。
映像業界は「長時間労働」「給料の低さ」「下積みの厳しさ」から「やめとけ」と言われることがあります。確かに大変な面はありますが、その分やりがいも大きい仕事です。

映像業界の職種①:企画・制作系
映像業界の仕事は大きく「企画・制作系」と「技術系」に分かれます。
企画・制作系は作品づくりの方向性を決め、チームをまとめて完成まで導く役割です。企画を立てたり台本を作ったり、スケジュールや予算を管理するなど、全体の進行に関わるのが特徴です。
代表的な職種
- プロデューサー
- ディレクター
- アシスタントディレクター(AD)
- 放送作家・脚本家 など
①プロデューサー
プロデューサーは映像作品全体を統括する立場で、いわば「現場の総監督」です。
番組や映画の企画を立て、制作費を集め、スタッフやキャストを決定し、完成まで全体を管理します。現場での判断力やリーダーシップ、さらに幅広い人脈やコミュニケーション力が求められます。
特別な資格は必要ありませんが、ビジネス的な感覚や企画力が重要です。経験を積むことで影響力の大きな仕事に携わることができます。
②ディレクター
ディレクターは、映像作品の演出を担当するポジションです。
企画や台本をもとに「どんなシーンを、どう見せるか」を考え、カメラマンや出演者に指示を出して現場を動かします。編集にも深く関わり、作品の最終的な方向性を決める役割です。
求められるのは創造力と判断力、そしてチームをまとめる力。
資格は不要ですが、演出の知識や実践経験が大切で、まずはアシスタントディレクター(AD)から経験を積むのが一般的です。
③制作デスク
制作デスクは、企画や現場がスムーズに動くようにサポートする役割です。
スケジュールの調整、資料の準備、スタッフや出演者との連絡など、いわば「現場の司令塔の事務局」のような存在です。華やかさは少ないですが、確実な仕事ぶりが作品全体の進行を支えます。
必要な資格はありませんが、パソコンスキルや事務処理能力、気配りやコミュニケーション力が重要です。
映像業界の流れを広く知ることができるため、他職種へのステップアップにもつながります。
④構成作家
構成作家は、番組や映像作品の「台本」や「進行構成」を作る仕事です。
特にバラエティや情報番組では、番組の流れや企画内容を文字で組み立てるため、笑いや展開を生み出すクリエイターでもあります。ドラマやアニメでは脚本家に近い役割を担うことも。
必要な資格はありませんが、発想力と文章力、流行や世の中の動きをとらえる感性が求められます。
フリーランスとして活躍する人も多く、自分の企画や言葉が番組を動かす魅力的な仕事です。

未経験でも安心!基礎からしっかり学べるカリキュラム
映像業界の職種②:技術系
映像業界の仕事は「企画・制作系」と「技術系」に分けられます。
技術系は撮影や音響、照明、編集など、実際に映像を形にする“職人”のポジションです。カメラや音響機材、編集ソフトを使いこなし、作品のクオリティを左右する重要な役割を担います。
代表的な職種
- カメラマン
- 映像編集(エディター)
- 音響スタッフ
- 照明スタッフ など
①カメラマン
カメラマンは映像を撮影する専門職です。
映画やドラマ、番組などで構図やアングルを考え、最適な画を撮影します。
撮影機材の知識や技術力に加え、監督やディレクターの意図をくみ取る感性が必要です。
資格は必須ではありませんが、カメラ操作や映像機器の扱いに習熟していることが重要です。
②音声
音声スタッフは撮影現場でマイクを操作し、セリフや環境音をクリアに収録します。
ガンマイクやワイヤレスマイクを駆使し、不要な雑音を避けながら必要な音を拾うのが役割です。
特別な資格は必要ありませんが、音に敏感で細やかな気配りができることが強みになります。
③音響オペレーター
音響オペレーターは、スタジオやイベント会場で音響機材を操作し、音のバランスを整える仕事です。
マイクやスピーカーのセッティングを行い、出演者の声やBGMを最適に届けます。
資格は不要ですが、機材知識や音響学の基礎があると有利です。
④照明オペレーター
照明オペレーターは、舞台や撮影現場で光を操る仕事です。
出演者をきれいに見せたり、作品の雰囲気をつくるために照明をデザインします。色彩や光の強弱をコントロールするセンスが必要です。
資格は特にありませんが、電気工事士や照明に関する知識が役立ちます。
⑤MAミキサー
MAミキサーは、収録済みの音声や効果音、BGMを映像に合わせて調整・合成する仕事です。
セリフを聞き取りやすくしたり、効果音を加えて臨場感を演出します。
音響に関する資格は不要ですが、音楽や音響編集ソフトのスキルがあると強みになります。
⑥編集
編集スタッフは、撮影した映像をつなぎ合わせ、作品として完成させる役割です。
不要な部分をカットしたり、映像をリズムよく並べ替えたりして、見やすく仕上げます。編集ソフトを扱うスキルが必須で、資格は不要ですが映像編集検定などを学んでおくと就職に有利です。
⑦CGクリエイター
CGクリエイターは、映像にコンピューターグラフィックスを加える仕事です。
アニメーションや映画の特殊効果、ゲーム映像など幅広く活躍します。
高度なソフトを扱う技術やデザインセンスが必要です。
資格は不要ですが、CG検定や専門学校でのスキル習得が役立ちます。
⑧サウンドクリエイター
サウンドクリエイターは、映像に合わせてオリジナルの音楽や効果音を作り出す仕事です。
作品の雰囲気を決める大切な要素で、作曲やアレンジのスキルが必要です。
資格は必須ではありませんが、音楽理論やDAWソフトの操作技術を持っていると強みになります。
⑨美術・スタイリスト
美術スタッフやスタイリストは、映像の世界観を形にする役割です。
セットの装飾や小道具の準備、衣装のコーディネートを担当し、作品のリアリティを高めます。
資格は必要ありませんが、美術やデザイン、ファッションの知識が活かされます。
⑩ヘアメイク
ヘアメイクは出演者の髪型やメイクを担当し、役柄やシーンに合わせてイメージをつくりあげます。
作品の雰囲気やキャラクター性を左右する重要な仕事です。
美容師免許があると幅広く活躍できますが、必須ではなく、ヘアメイク専門の学校で学ぶ人も多いです。

映像業界の平均年収
映像業界の平均年収はおおよそ300万~500万円ほどといわれています。
ただし、職種や経験年数によって差が大きいのが特徴です。
新人のうちはアシスタント業務が中心となり、年収200万~300万円台からスタートすることが一般的です。
一方で、ディレクターやプロデューサー、カメラマンや編集のスペシャリストなど、実力や実績を積んだ人は年収600万円以上になることもあります。
フリーランスで成功すれば、さらに高収入を得るチャンスもあります。
また、近年はYouTubeや動画配信サービスなど新しい分野が拡大し、企業案件や広告動画の需要が増えているため、活躍の場が広がっています。収入面だけを見れば厳しい印象もありますが、スキルを磨き続ければ安定したキャリアを築ける可能性が十分ある業界です。
映像業界に向いている人の特徴
映像業界に向いている人の特徴は、大きく分けて「発想力」「コミュニケーション力」「粘り強さ」の3つです。
まず、新しい企画や表現方法を考える発想力は、番組や作品に独自性を生み出すために欠かせません。
次に、映像制作は監督・スタッフ・出演者など多くの人が関わるため、周囲と意見をすり合わせながら進める協調性やコミュニケーション力が必要です。
また、撮影や編集は長時間に及ぶことも多く、トラブルや修正対応も頻繁に発生するため、粘り強く取り組める人が活躍できます。
さらに、流行やテクノロジーの変化が早い業界なので、新しいことを学び続けられる柔軟さも重要です。
「人を楽しませたい」「面白いものをつくりたい」という情熱を持っている人は、この業界で大きなやりがいを感じながら働けるでしょう。
映像業界の将来性
映像業界はこれからますます広がる可能性を秘めています。
YouTubeやTikTokなどのSNS動画や、企業のプロモーション動画の需要は年々増加中で、個人でも活躍できるチャンスがあります。さらに、AI技術や最新の映像機材の進化で、これまでにない表現や効率的な制作も可能になってきています。
好きなことを仕事にしたい人や、新しい映像表現に挑戦したい人にとって、これからも夢を形にできる魅力的な業界です。

映像業界を目指すなら、国際映像メディア専門学校
映像業界で活躍したいなら、国際映像メディア専門学校はいかがでしょうか。
現場で役立つ技術や知識を学べるだけでなく、プロのクリエイターから直接指導を受けられる環境があります。企画・制作から撮影、編集、音響まで幅広く体験できるので、自分に合った分野を見つけやすく、将来の夢を具体的に描くことができます。
国際映像メディア専門学校で、映像の世界に一歩踏み出してみましょう。
執筆者

この記事は、i-MEDIA事務局が記事の監修をしています。